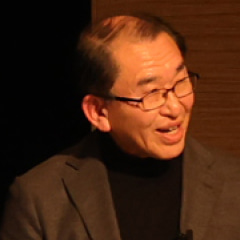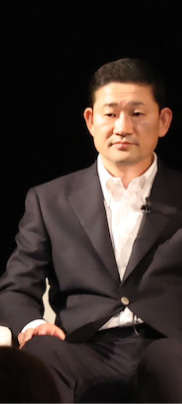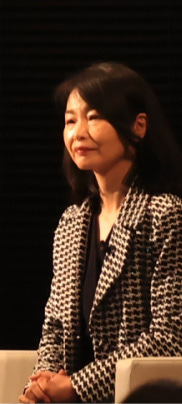7年前のビジョンの達成度で現在を評価
萩原: 前半のテーマは「マーケティング・リサーチ産業ビジョンを振り返る」です。これは、デジタル化が進展した2017(平成29)年に、新たな時代に向けた価値提供を提起した内容でした。本日は、4テーマに沿ってビジョンの達成度を評価します。第1は「生活者を最も理解した代弁者になる」です。できているとお考えのお二人からお願いします。
鈴木: オンライン・オフラインともに、調査票が正しければ、そこから導く結果が“生活者の代弁者”となる力になり、リサーチ会社がその役割を果たすと考えます。
高山: 様々な業界の方とお仕事をする機会がありますが、最も生活者を重視して語っているのは私たちだと感じますし、これができなければリサーチャーではないと思います。
萩原: 残るお二人は、どこがまだ足りないと思われますか。
佐々木: 本当にできていれば、マーケティングシーンで当社がもっと選ばれるはずで、私たちを介さずに消費者の声を取得する方法が増える今、深さと継続性を高めるべきです。
五十嵐: インサイト産業をはじめ、もっと広範囲に生活者を理解したいと言うお客様のニーズが市場規模で4,500億円、リサーチ業界全体が2,500億円で、このギャップがまだ足りないと語っています。今一度生活者を最も理解した代弁者になるべきと考えました。

萩原:第二のテーマ「ビッグデータビジネスの中心的存在になり価値創出をリードする」はいかがでしょうか。
五十嵐:リサーチ業界が持つデータが限定的なのに対し、様々な業界がビッグデータを持ち、役割分担が大きく変わっています。
鈴木:現状はせいぜい1万単位で、何百万のデータを処理するスキームは立て難いですし、多くの会社はビッグデータの分析を、内製化や提携で行う体制にはなっていませんね。
高山:弊社はビッグデータであるPOSデータを取り扱いますが、市場計測データの段階で、違うビジネスの位相に届いていません。
佐々木:ビッグデータ活用の目的がより明確になるまでは、できる範囲を示して役割分担したいですね。活用の中心的存在にはなりたいですが限界はあると思います。
萩原:3つ目は、調査会社として「クライアントのビジネス的成功をドライブする存在になる」です。これは「時系列のデータをクロス集計する事例ではドライブする存在になり得る」とした鈴木さん以外は否定的ですね。
高山:クライアントのビジネス構造を理解し、方向性を示すまでが役割で、成功にコミットする勇気は持ち合わせていません。
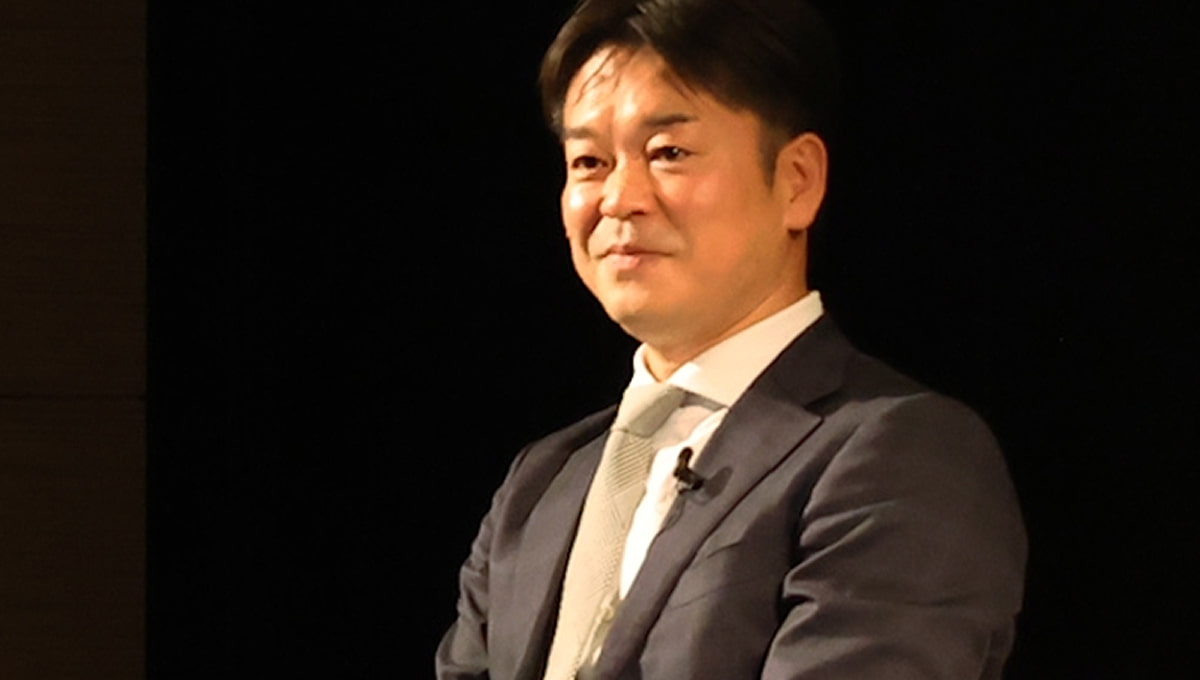
佐々木:個人で実践される方もいますが、会社単位では難しいですね。紋切型ではなく、調査から導かれる全ての可能性を伝えて、その先に繋げる姿勢が重要です。会社としてそこまでコミットすると宣言すべき時期です。
五十嵐:ファクトデータに基づく意思決定支援がリサーチビジネスの本質と考えますので、その領域の専門家として依頼されれば、リサーチャーとしては成功です。佐々木さんが言われた通り個人的に実践されている方はいて突破口は開きつつある気がしますが、ドライブする立場とは異なりますね。
萩原:最後は「多様な専門性を持つ異才の集まりになる」です。五十嵐さんは「できていない」という見解ですね。
五十嵐:例えば電話にストレスを感じる世代が現れ、営業職の捉え方も20代から50代で違います。インサイト産業化でデータエンジニアが必要とされ、より多様な年齢、分野の人材の必要に迫られる危機感からです。
鈴木:エンジニアリングやサイエンス、UX系やビジネスアーキテクトなどの分野で人材が流動化しており、魅力を高めて、異才が集まる集団にしてレイヤーを上げたいです。
高山:(「自分は昔ながらのリサーチャー以外だと思う方は挙手を」と会場に呼びかけて)チラホラという所ですが、10年前はほぼいなかったでしょう。人材募集にも多様性を感じますが、様々な会社がデータを持つようになり、人材が集まりにくいのは確かですね。
リサーチャーの個人的な思いに応える
萩原:リサーチャーにはエンジニアリング系にアート系、デザイン系など新たな領域の人材が必要とされてきていますね。
後半は「リサーチ業界従事者アンケートの結果を踏まえて考える」がテーマです。有効回答702名でリサーチ業界全体の約10%に回答いただきました。男女比半々で働き盛りの30代、40代も多く、会社規模もバランスよく集まりました。初めのテーマは「リサーチャーの個人的な想いに会社がどう応えられるか」です。給与・待遇をはじめ期待と満足のギャップが結果に出ています。
高山:幅広い産業を相手に様々な仕事ができて、成長できる業界なのに、これだけのギャップがあると緊急の対策の必要を感じます。
鈴木:成長したい社員との間でフィットアンドギャップが生まれているようです。今後、リサーチスキル以外の成長を求められたときに10年後を見据えてリサーチを定義付けする必要を感じました。
佐々木:このままでは業界からリサーチャー人材が流出する危惧があります。私も専門性を身に付けた先の業務も考えるべきと思います。マーケティングと真剣に向き合う方々と日々コミュニケーションできる環境は希少ですし、要件を整理してデータから解を導くスキルは稀有だと思うのですが。
五十嵐:座学では身に付かない新しい経験ができる業務内容や規模を創り、ジョブローテーションを提供しなければいけませんね。
佐々木:例えば専門的スキルやグローバル人材という言葉は抽象的です。自分のキャリアと向き合う皆さんは、ぜひご自分の将来を言語化して上司と話し合ってください。管理職の方もそうした観点で臨んでほしいですね。
高山:私たちが誇れるスキルや提供している価値を言語化する必要が、個人にも会社にもあると私も思いました。「生活者の声からインサイトを抽出できる」と言うよりも、他業界に通用するよう言語化して初めて自分たちが提供する価値に気付けると感じました。
五十嵐:彼らの定義をどう言語化するかに繋がりますね。リサーチャーのレポートを生産性分析すると80%の作業に対価が支払われていない。だからその80%に向けて仕事を取れば生産性が5倍上がります。AIやDXを導入してが本来発揮できる能力に振り向けることで、新たな職種を生み出せればと思います。

業界と協会が共同で事業領域を広げるべき

萩原:議論の流れを受けて「業界の未来像」に移ります。アンケートでは、市場調査以外への転職意向が転職希望者の約8割に上りました。転職検討理由で一番多い自分の専門性やスキルを他で活かしたいという動機は前向きですが、3番目に多い理由に業界の停滞を示唆する意見があります。自由回答では下請け業務という言葉が多く、アピールが足りないという指摘もあり事業領域の見直しや提供する価値の向上が必要という見方も出ました。そこで、リサーチ業界に良質な人材を呼び高い給与で付加価値の高い仕事をしてもらうには、どうすべきかを考えたいです。
五十嵐:業界全体の産業規模を上げる全体的な目標を据えて、業界の定義を変えてインサイトをはじめとする成長市場に矢印を向け、必要な人材を定義付けできれば、スムーズに走れると思っています。
高山:業界外への転職希望者が多いのは課題ですが、リサーチ業界で培ったスキルや、リサーチの価値に信念を持って転職されるのは、リサーチ業界にもプラスです。リサーチの価値を理解された方がクライアントにいないと、予算もいただけません。
萩原:業界の魅力を高めて付加価値を上げるという点はいかがですか。
高山:最近は、お客様も非常に勉強されていて、私たちも生半可でない勉強が必要です。コンサルタントにサポートを依頼した際、私たちの反応をメモする姿を見て、クライアントの意識を感じました。私たちも、お客様の側のミッションと評価基準を理解して、どう貢献するかを先んじて考える必要があります。
五十嵐:コンサルタント業界の給与の高さは、経営に直結した話ができて売上を上げる提案ができるからです。リサーチャーだって同じ要素スキルを持っているのに少し偏っているかもしれない。コンサルティングに拡張した方が付加価値は上がると思うので、経営陣も含め業界が動くべきだと思います。
佐々木:コンサルタントを使う理由は、何を投げても必ず客観的な意見を返すからです。ただ私もデータとマーケティング領域でこの役割は担えると思うので、業界と協会が二人三脚でインサイトも含めた新たなバリューアップの方向に進むべきと思います。
五十嵐:皆さんの処遇を高めるには、短期的には生産性を上げるしかない。私たちの試算では、1年間で30%は上がっているので、これは結果が出せます。またAIの本質は述べた通りで、これは真っ先にやるべきです。
佐々木:私も同感で、AIは大幅なスピードアップに繋がりますが、これはお客様にとっても重要な価値で、短期的に行うべきですね。中長期的には、お客様との間で、リサーチ業界が提供できる価値を明文化する必要があります。コンサルタントファームと比較すると、デジタルマーケティングやAI活用の経験が違うのみで、リサーチャーが同じ場所に到達する可能性はあると思っています。
萩原:コンサルタントと比較してもリサーチャーが引けを取ることはない、従来の役割を捉え直し、提供する価値を上げてゆくべきという点でおよそ意見の一致を見たようです。座談会の最後は五十嵐会長にお願いします。
五十嵐:今回のようなビッグワードのテーマでこれだけ多くの方が集まったことに皆さんの真剣さが伝わりました。改めて横の連携の大切さを感じます。今、30代、40代の中堅世代で動いている企画があるので、楽しみにしていただきたいと思います。